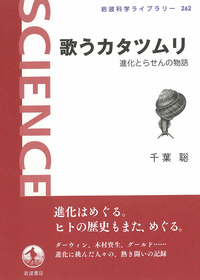よい本 1
- 畑将貴『右利きのヘビ仮説――追うヘビ、逃げるカタツムリの右と左の共進化』(東海大学出版会、2012年)
- 千葉聡『歌うカタツムリ――進化とらせんの物語』(岩波書店、2017年)
- 大場裕一『恐竜はホタルを見たか――発光生物が照らす進化の謎』(岩波書店、2016年)
- 上村佳孝『昆虫の交尾は、味わい深い…。』(岩波書店、2017年)
- 細川貴弘『カメムシの母が子に伝える共生細菌―必須相利共生の多様性と進化― 』(共立出版、2017年)
- 青木重孝『兵隊を持ったアブラムシ』(丸善出版、2013年)
- 太田悠造『海のクワガタ採集記―昆虫少年が海へ―』(裳華房、2017年)
- 塚谷裕一『森を食べる植物――腐生植物の知られざる世界』(岩波書店、2016年)
最近読んだよい本たちの紹介。すべて生き物の本。
畑将貴『右利きのヘビ仮説――追うヘビ、逃げるカタツムリの右と左の共進化』(東海大学出版会、2012年)
カタツムリの殻の巻き方には右巻きと左巻きの2通りある。尖ったほうを上にして殻の口を正面に向くようにしたとき、その口が右にくれば右巻きで左なら左巻き。実は大部分のカタツムリは右巻きの殻を持っている。まれに突然変異で左巻きの個体が生まれるが、交尾の都合で子孫を残しにくいというハンディキャップを負うため左巻きの遺伝子はなかなか広がらない。ところが、琉球列島の一部には種全体で左巻きが多数派を占めるカタツムリがいる。左巻きが生存に有利になるような淘汰圧、たとえば右巻きのカタツムリの捕食に特化したヘビがいるのではないか……という学部生時代の着想から著者の研究が始まる。
その「右利きのヘビ仮説」を論文として出版するに至るプロセスがいきいきと語られているのがこの本。実際に著者の最初のアイデアは検証されて裏付けを得るのだが、このひとつのアイデアを確かめるための道のりのなんと長いことだろう。まず初めに別々の文献にあった「左巻きのカタツムリ」と「カタツムリ食のヘビ」に関する記述が頭のなかで結びつく。そのヘビ、イワサキセダカヘビが実際に左右非対称な顎をもつことを図で確かめ、骨格標本で観察し、同じセダカヘビ科のヘビの標本をたくさん取り寄せて自力でX線撮像をして統計をとり……というのはまだ序の口。生きたイワサキセダカヘビを捕獲するため西表島に渡る。そこでの調査の様子がまた面白い。言わずと知れたイリオモテヤマネコをはじめ固有種に満ち満ちた亜熱帯の森で、虫にたかられ毒蛇サキシマハブを避けながらただ一種イワサキセダカヘビを探す。中には陸生のホタルの幼虫もいて林床で発光しているとか。夜間調査のためのノウハウ(建設業向けの長靴がよいとか)も書かれていてこのフィールドワークの様子が鮮明に浮かび上がる。
持ち帰ったヘビとペットショップで買ったヘビ(絶滅危惧種の売買にあたるが「なりふり構っていられなかった」と振り返る)を使って実験室で行うのはカタツムリを捕食する姿のビデオ撮影。右巻きと左巻きのカタツムリを用意することや撮影環境などに四苦八苦しながらも、ついに「右利きのヘビは左巻きのカタツムリを食べるのが不得意である」ということの数値的統計的な裏付けを得る。
本書の副題は「追うヘビ、逃げるカタツムリの右と左の共進化」。「右利きのヘビ仮説」を通して見えるのは進化。左巻きのカタツムリは右利きのヘビから逃げやすいという事実から見えるのはあくまでその一端だけれど、確固としたデータを基に左巻きのカタツムリが進化してきた理由の解明に近付いた。その素晴らしさよ。
著者はコラムの中でジョナサン・ワイナー『フィンチの嘴』(早川書房/2001年/原著1994年)を紹介している。『フィンチの嘴』で主役となるのは、ガラパゴス諸島のフィンチの嘴の長さ・形をはじめ餌の種類や量などを計測しつづけたグラント夫妻。執念深いまでに集められた数値的なデータを基に、ともすれば机上の理論になりかねない「進化」に裏付けを与え、その実態を浮かび上がらせてゆく。『フィンチの嘴』を読むと、改めて『右利きのヘビ仮説』で行われた観測や行動実験の数々の意義が理解できる。進化は数値で示すものだと。
『右利きのヘビ仮説』のエッセンスは以下の記事でも読める。
『右利きのヘビ』で解く,左巻きカタツムリの謎
https://www.sbj.or.jp/wp-content/uploads/file/sbj/9303/9303_index.pdf
著者ウェブサイト
Hoso's Website
余談。自分はこの本を神保町の本祭りの東海大出版の屋台で買った。定価2000円+税のところ600円。以前から気になっていた本だったが、ようやく買って読んでみると心から感動して生物本への関心が再燃した結果このブログ記事を書いている。いちばんおすすめしたい本。今すぐ手に入れて読んでほしい。
千葉聡『歌うカタツムリ――進化とらせんの物語』(岩波書店、2017年)
「秘島探検 東京ロストワールド 第1集 南硫黄島」で「コダマ」と呼ばれる陸貝:コダマキバサナギガイを探していた研究者がこの本の著者。
NHKスペシャル | 秘島探検 東京ロストワールド第1集南硫黄島
あの1時間足らずの番組では物足りないな~~と思っていたら首都大学東京の刊行物で詳しく報告されていた。
小笠原研究 No.44 > 和田慎一郎, 千葉 聡「南硫黄島の陸産貝類群集の多様性」(pp.315-330)
2018 | 小笠原研究委員会
それはともかく、この『歌うカタツムリ』は進化論がその黎明期から今に至るまでいかにカタツムリを利用しながら発展してきたかを落ち着いた筆致で語った本。ある一群の生物種(ここではカタツムリ)の観察をもとに進化の実際に迫り理論を組み立てていく、という点でやや『フィンチの嘴』に趣が似ている。
自然選択は考え方としてはわかりやすいものだけれど、定量的に論じるにはやはり数学が必要になる。集団遺伝学の創始者であるフィッシャー・ホールデンや、著書『ワンダフル・ライフ』や断続平衡説で有名なグールド、中立説の木村資生がその流れの中に位置づけられる。その理論の着想・検証のためには、数が多い・捕まえやすい・殻の形状を定量化しやすい・収集が楽しいカタツムリや、あるいは化石種の貝がモデルとして都合がよかった、ということらしい。
本書のタイトルはハワイ島の「歌うカタツムリ」の伝承から来ている。ハワイ島の固有種であったハワイマイマイたちは森の中で歌うような音をあげると信じられていた。しかし現在その真偽を確かめる術はもうない。というのも、アフリカマイマイ駆除のために導入されたカタツムリ食のカタツムリ、ヤマヒタチオビに滅ぼされてしまったから。
歴史あるカタツムリによる進化研究の現在側の端で、小笠原諸島を中心に陸貝の研究を続ける著者たちグループの研究にたどり着く。小笠原諸島にも外来種の脅威は訪れており、陸生の肉食プラナリア、ニューギニアヤリガタリクウズムシによって父島の陸貝はほぼ野生絶滅してしまった。このことは簡潔に書かれているだけだけれど、種を滅ぼしてしまうことで失われたものがいかに大きいか、改めて知る。
大場裕一『恐竜はホタルを見たか――発光生物が照らす進化の謎』(岩波書店、2016年)
めちゃくちゃいいタイトルだ……。「恐竜はホタルを見たか。」今と同じ風景を、やがて滅んでしまう恐竜たちも知っていたか、というどこかうら寂しさを感じさせる問い……。
結論からいうと「おそらく見ていた」で、これはホタル科を対象とした分子系統解析から、その誕生が白亜紀にまで遡るという著者たちの研究成果からきている。また、ホタルルシフェリンを酸化して発光反応を引き起こす酵素ホタルルシフェラーゼについて、広く生物が持つ脂肪酸分解酵素がその由来であろうと特定している。
「光る生物」として真っ先に思い浮かべられるのはそのホタルだが、実は比率でいうと大半の光る生物は海にいる。2008年のノーベル化学賞を受賞した下村脩博士の研究で有名なオワンクラゲもそのひとつ。ちょっとびっくりすることに、オワンクラゲは自力でルシフェリンを作れないらしい。酵素のルシフェラーゼは生合成できるが、基質であるルシフェリンは外部から取り入れないと光れないということ。そのクラゲも使っているルシフェリンであるセレンテラジン(ルシフェリンは総称)は他にもたくさんの海の発光生物が採用していて、ほとんどが自力合成できない。では誰が作っているかというと、微小な甲殻類プランクトンであるコペポーダ(カイアシ類)がその候補に挙がる。そしてたどり着くのは、海の生き物にとってありふれた栄養源であるコペポーダが光るからこそ、海では生物発光がありふれたものになったのだろうという仮説。系統樹上のいろいろな位置にみられる生物発光を概観するところから始まって、結構マニアックな話の一端に触れられて楽しい。
上村佳孝『昆虫の交尾は、味わい深い…。』(岩波書店、2017年)
岩波化学ライブラリー3冊目。2017年のイグノーベル賞を受賞したトリカヘチャタテの研究グループの一人による著書。受賞理由は「ある洞窟棲昆虫の雌ペニス、雄ヴァギナの発見。」ちょうどこの本を読んでいたときに続報があった(ちなみにこの掲載誌eLifeはフリー)。
トリカヘチャタテのメスはペニスの他にコックも持つ-切替弁を持つ生物を世界で初めて発見-:[慶應義塾]
A biological switching valve evolved in the female of a sex-role reversed cave insect to receive multiple seminal packages | eLife
昆虫の交尾器(ゲニタリア)といえばとにかく複雑な形をしているが、種を判別するための唯一の手段がその小さな交尾器を見分けることであったりして研究者泣かせらしい。しかし世代を繋ぐための最重要器官である以上その形にも意味があって、しかも種間での変異が大きく解き明かすべき謎は尽きない。
たとえばトンボの雄は雌が前に交尾した雄から受け取った精子を掻き出すための物騒なトゲだらけの性器を持っている。昆虫では雌は一度受け取った精子を貯めて使うため。しかし雄は対抗手段も発達させていて、雌が再び交尾しないようガードするための副性器も持っている。
著者が最初の研究のターゲットとしたのはハサミムシ。ハサミムシの雄は長い挿入器を、雌の細長い受精嚢に詰まった他の雄の精子を掻き出すために発達させていることを突き止める。種によって左右に対で持っていたり、一方だけだったり、中央に一本だけになっていたりと、ここでも「右利き・左利き」の話題が出てくる。
トコジラミもまた左右対称性が破れている昆虫の一例。このトコジラミ、雄が鋭い交尾器を雌の脇腹に刺して体内に精子を注入し、雌の血液を介して卵巣に向かわせるという異常な交尾形態を持つ。その際雌が最初に精子を貯めるのが右脇腹に持つスーパーマリッジと呼ばれる腔で、大半の雌は左脇腹には持たない。しかし稀に両側に持つ個体がおり、著者はその右スーパーマリッジが正しく機能することを証明したものの、そのようなコストを抱える意義を未解明のまま残す。
交尾器は見た目が面白いばかりでなく、機能や形態に単に配偶子をやりとりするだけではない雌雄間の競争が現れる。そういうところが味わい深いようだ。
細川貴弘『カメムシの母が子に伝える共生細菌―必須相利共生の多様性と進化― 』(共立出版、2017年)

カメムシの母が子に伝える共生細菌 ―必須相利共生の多様性と進化― / 細川 貴弘 著 辻 和希 コーディネーター | 共立出版
アブラムシのついた植物がベトベトになるのはなぜか?あれは植物から啜った篩管液のうち過剰な糖分を排出しているのだ。実は篩管液は肝心の必須アミノ酸が非常に乏しい。この「栄養の偏った食糧」から必要な栄養を得るため、アブラムシはブフネラという共生細菌に必須アミノ酸の合成を任せている。アブラムシに限らず共生細菌による栄養の合成は様々な昆虫で見られ、セミ-ホジキニア、ツェツェバエ-ウィグルスワーシア、トコジラミ-ボルバキア……等、それぞれ違った組み合わせで昆虫-細菌間の共生関係が結ばれている。昆虫側は細菌なしでは生きられないほどに依存していて、細菌側も昆虫の体内という安全な環境から抜け出せなくなっている。これを必須相利共生と呼ぶ。
カメムシもまた細菌との共生関係を結んだ昆虫のひとつ。しかし他の昆虫たちとは異なる特徴を持っている。それは母から子へ共生細菌を受け渡す過程にある。普通、宿主昆虫は共生細菌を宿した「菌細胞」から直接、つまり体内で卵に共生細菌を分け与えることで次世代に繋いでいる(垂直伝播)が、カメムシは産み落とされた段階の卵の中には共生細菌が入っていないのだ。従って子は母親の体外で共生細菌を貰わなくてはならないが、その方法が種ごとに異なっている。
たとえば、マルカメムシ類は卵塊とともに黒い粒を産み落とす。この黒い粒に共生細菌が詰まっており、幼虫は孵化後にこれに口吻を突き刺してなかから共生細菌を吸う。孵化するまで卵の世話をすることで知られるベニカメムシは、孵化直前に共生細菌の混ざった白い粘液を卵塊にかける。
面白いのは受け渡しの方法だけではない。体外で共生細菌のやりとりをするため、たとえば抗生物質を使って細菌を除去したり、本来の共生細菌とは違った細菌に入れ替えたりすることができるのだ。著者はそのような実験を試すなかで、共生関係がいかに進化してきたかを調べようとしている。
著者ウェブサイトでは本書にも引用されている動画が見られる。子カメムシがかわいい。
Hosokawa Takahiro - 研究内容
青木重孝『兵隊を持ったアブラムシ』(丸善出版、2013年)

兵隊を持ったアブラムシ - 丸善出版 理工・医学・人文社会科学の専門書出版社
昆虫の社会性がハチ・シロアリ類だけではなくアブラムシにもみられることを発見したのがこの本の著者。昆虫の社会性……色々イマジネーションが刺激されて良い。
アブラムシの分類学者を目指していた著者は、ある日採集したワタムシ(ふわふわしたワックスをまとうアブラムシの仲間)の中に、奇妙な幼虫を見つける。それは普通の幼虫に比べて短い口吻と長くて太い前脚を持つ一令幼虫だった。試行錯誤の末、この「短吻型幼虫」が外敵に対する攻撃を専門とした不妊の個体であることが判明する。
アブラムシの仲間には虫癭(虫こぶ、ゴール)を作るものもいる。台湾に生息する、ウラジロエゴノキに巣を作るウラジロエゴノキアブラムシは、人が近づくと落下して刺すらしい。そんな記述を目にし、著者は実際に確かめにゆく。そしてやはり兵隊であった二令幼虫がこの攻撃に携わっていることを突き止める。
こうしてさまざまなアブラムシ種の兵隊幼虫と社会性を見つけていくとともに、データを集めながらこのような分業制を説明するために数理モデルを構築していく。
最初の研究は40年前に遡り、この本も元々どうぶつ社から1984年に出版され絶版となっていたものの復刊。社会性アブラムシに関してはその後色々面白いことが分かってきているらしい。
ツノアブラムシのゴール、社会性、生活環 | 公益財団法人 藤原ナチュラルヒストリー振興財団
アブラムシが持つ表面加工技術 | 東京大学
産総研:兵隊アブラムシの攻撃毒プロテアーゼ
太田悠造『海のクワガタ採集記―昆虫少年が海へ―』(裳華房、2017年)
「ウミクワガタ」この表紙に描かれているやつがそれ。素晴らしく単純明快なネーミングだ。ただしクワガタムシのような顎を持っていても昆虫(六脚亜門)ではなく甲殻類(甲殻亜門)、特にダンゴムシやオオグソクムシ、タイノエなどと同じ等脚目の仲間。
大きな顎を持つのはやはりクワガタムシと同じく雄の成体だけ。雌雄ともに幼生の間は魚類の体液を吸う寄生者。成体になって繁殖期に入ると魚から離れて何も食べずにつがう。
著者は琉球大学在籍時にこの研究を始める。沖縄の海に潜ったり、砂浜を掘ったりしながらこの小さなウミクワガタを探す日々。「見過ごされた動物」と言うだけあって、見つかっていなかった種が非常に多く、新種発見の喜びを著者の記録から感じ取ることができる。体長数ミリの新種掲載のために正確なスケッチをする様子もおもしろい。
ただ、こういうマニアックな生物の研究にはやはり金銭的な過酷さがつきもののようで、著者自身の体験が生々しく記述されている。
塚谷裕一『森を食べる植物――腐生植物の知られざる世界』(岩波書店、2016年)
日の当たらないじめじめとした林床にひっそりと生える奇妙な形をした透き通った植物……というとビジュアルがなんとなくわかると思うが、この本のテーマである「腐生植物」がそれ。「森を食べる」というのは彼らが光合成をやめ、菌類に寄生していることから。根を通してキノコから栄養を奪っているのである。だから動物の遺骸から栄養を得ているかのような印象を与える「腐生植物」というのは誤解を招く呼び名で、「菌寄生植物」とするべきらしい。
この本を読むまで知らなかったことだが、蘭は蘭菌と呼ばれる菌類と共生して栄養を得ているらしい。そのような菌への依存が極限まで進んだのがこの腐生植物たち。ただし、ラン科に限らず色々なグループでこの腐生植物化は起こっている。
光合成色素の緑色を捨てたことで得た透き通った白さだけではなく、一風変わった形をとる花が非常に神秘的。ちなみにこの本の写真はすべてカラー。
ボルネオでの新種発見のいきさつも書かれており、こう言ってしまって良いものか、「高尚な道楽」っぽさがすごい。